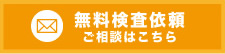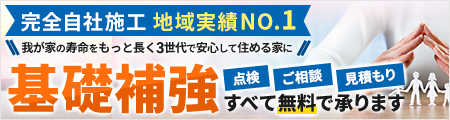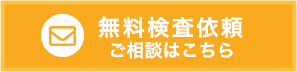基礎コンクリートにポツポツと空洞が見える場合、それは「ジャンカ」や「豆板」と呼ばれる欠陥の可能性があります。
ジャンカは床下など普段目にしにくい場所で起こりやすく、放置すると基礎の強度低下や建物全体の安全性に影響があります。
ALT(アルト)では、これまで数千件以上の基礎点検・補修の実績をもとに、ジャンカの早期発見と最適な補修方法を提案しています。本記事では、ジャンカの発生原因や建物へのリスク、さらに具体的な補修方法まで、豊富な施工経験に基づいた知見を交えて詳しく解説します。
基礎の不具合やジャンカの存在に不安がある方は、ぜひ最後までお読みください。
基礎コンクリートのジャンカ(豆板)とは

ジャンカとは、基礎コンクリート打設の際に骨材(砂利)が偏って集まり、空隙やスカスカした部分ができる現象のことです。見た目が豆を散らしたように見えることから「豆板」とも呼ばれます。
一見すると小さな欠陥に見えますが、放置すると建物の強度や耐久性に悪影響を及ぼす可能性があります。
基礎にジャンカ(豆板)が発生する理由は?
ジャンカは、基礎コンクリートの施工中に起こる欠陥で、多くの場合は施工不良が原因で発生します。
コンクリートは「セメントペースト」「骨材(砂利など)」「水」を混ぜた材料ですが、骨材が鉄筋や型枠の端に偏って固まると、空隙ができてジャンカになります。骨材は重いため沈みやすく、振動機(バイブレーター)でしっかり撹拌しないと偏りが生じます。
通常は職人が注意して撹拌しますが、施工不良や技術不足によってジャンカが発生することがあります。さらに、高い場所から生コンを打設すると材料が分離しやすくなり、ジャンカの発生リスクが高まります。
ジャンカが建物に及ぼす2つのリスク
ジャンカは基礎コンクリート内部に発生するため、普段は気づきにくい欠陥です。しかし、対応を怠れば建物に次のような2つのリスクが生じる恐れがあります。
1.基礎コンクリートの強度低下
ジャンカ部分ではコンクリートが十分に密着していないため、本来の強度を発揮できません。
その結果、建物を支える力が弱くなり、地震や台風などの外部からの力に対して脆くなる恐れがあります。状態がひどい場合には、手で触れただけでもコンクリートがポロポロ落ちてしまうことがあります。
2.基礎コンクリート劣化進行
空隙があると水分や空気が入り込みやすくなり、鉄筋のサビやコンクリート自体の劣化を早めます。
錆びた鉄筋は膨張するため、ひび割れや剥離といったトラブルが起こり、場合によっては鉄筋が外部に露出する爆裂現象に発展することもあります。こうした理由から、早めの補修が重要です。
ALT(アルト)では、通常のジャンカ補修に加えて、高強度で耐久性に優れたアラミド繊維シートを用いた補強工法を採用しています。
この工法により、一般的な補修だけでは難しい基礎の強度と耐久性を、長期にわたってしっかりと確保することが可能です。なお、施工の具体的な手順や効果については、記事後半で詳しくご紹介します。
基礎コンクリートのジャンカ(豆板)の状態別補修方法
ジャンカの補修は、状態によって方法が変わります。ここでは、一般的な状態ごとの目安と補修方法をご紹介します。
Aレベル:健全
健全な基礎の状態です。この段階ではジャンカ補修の必要はありません。
Bレベル:軽度
骨材が表面に露出していますが、叩いたり削ったりしても剥がれない程度の状態です。この場合は、ポリマーセメントペーストを塗布して補修します。
Cレベル:中度
露出した骨材を叩くと剥落することもある状態です。ポリマーセメントペーストを塗布した後に、ポリマーセメントモルタルで充填して補修します。
Dレベル:重度
鉄筋が露出し、バラバラと連続的に剥落することもある状態です。この場合は、不要な部分をはつり取って健全な部分を露出させ、その後に無収縮モルタルを充填して補修します。
Eレベル:深刻
コンクリート内部に多くの空洞が見られる状態で、砂利を叩くと連続的に剥落します。深刻度が高いため、不要な部分をはつり取って健全な部分を露出させた後、コンクリートを打ち替えて補修します
ALT(アルト)が行っている基礎のジャンカ補修工法と実例
基礎コンクリートのジャンカに対して、安全性と耐久性を最優先に考えた補修工法を採用しています。基礎の強度に影響する脆いジャンカ部分を丁寧に取り除き、専用の補強材で再充填することで、しっかりと基礎の強度を回復させます。
なお、施工前には現場調査を行い、ジャンカの位置や規模に応じて最適な補修方法を選定し、安全で確実な施工を実現しています。
基礎のジャンカ補修事例を紹介
実際に行ったジャンカ補修作業の流れを6つのステップでご紹介します。施工前の状態から、補修・補強・仕上げまでの流れをイメージしていただけますが、実際の作業内容や手順は、ジャンカの規模や基礎の状態によって変わる場合があります。
1.ジャンカ補修:施工前の状態の確認

施工前の基礎コンクリートのジャンカの状態です。コンクリートに空洞や骨材の偏りがどの程度あるかを見ることで、補修の必要性や範囲を判断していきます。
2.ジャンカ補修:モルタル塗布

ジャンカ部分にモルタルを充填し、表面を平滑に整えました。基礎の初期強度を回復させる大切なステップです。
3.基礎補強:準備作業

モルタルでの補修後、基礎全体を補強するための準備を行います。施工前には表面の清掃や下地処理を行い、補強材がしっかり定着する状態に整えます。
4.基礎補強:下処理剤を塗布

基礎補強専用の下処理剤を塗布し、補強材との接着性を高めます。これにより、補強効果が長期間持続します。
5.基礎補強:アラミド繊維シート貼り付け

強度に優れたアラミド繊維シートを基礎に貼り付けることで、基礎の強度を補強し、耐久性を大幅に向上させます。
6.基礎補強:仕上げの保護補強剤塗布

最後に保護補強剤を重ね塗りして施工完了です。これにより、建物の安全性を長期的に確保できます。
ALT(アルト)のジャンカ補修の費用目安・保証について
ジャンカ補修の費用は、規模や補修範囲によって異なりますが、目安として基礎35mの補強で約70万円程度です。実際には現場の状態を確認したうえで最適な方法をご提案し、お見積もりをご提示しています。
なお、施工後には10年間の保証をお付けし、さらに毎年1回は無償で点検を実施。補修した箇所を継続的に見守ることで、長期的な安心をお届けします。
また、関東から関西まで複数の営業所を構えており、広いエリアに対応可能です。遠方からのご依頼でも出張交通費はいただいておりませんので、安心してご相談ください。
基礎のジャンカ(豆板)を見つけたらすぐ専門業者へ
ジャンカは放置すると基礎コンクリートの劣化を進め、建物の耐久性を低下させます。地震や台風など外部からの力を受けた際、基礎が十分に支えられなくなる恐れもあり、早めの対応が欠かせません。
見た目に異変がなくても、内部で劣化が静かに進行していることがあります。小さな空洞やひび割れが広がり、鉄筋にサビが発生すると、コンクリートの膨張やひび割れを招くこともあります。このような状態は素人には判断が難しく、自分で補修することはできません。
基礎コンクリートに異常を感じたら、速やかに専門業者に点検を依頼しましょう。
ALT(アルト)では、ジャンカや基礎のひび割れに関する無料相談・現場調査を承っております。経験豊富なスタッフが状況を丁寧に確認し、最適な補修方法をご提案いたします。
まずはお気軽に、下記フォームよりご連絡ください。